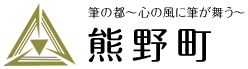個人町県民税
個人の町・県民税は、前年の1月から12月の間に一定以上の所得があった人に対して課される税金で、一年間の所得に応じて課税される「所得割」と、広く均等に一定の税額が課税される「均等割」があります。
なお、令和6年度からは個人の町・県民税を賦課徴収する際に、国税である森林環境税を町があわせて賦課徴収することとなっています。
納税義務者
個人の町・県民税・森林環境税の納税義務者は、次のとおりです。
|
区分 |
町・県民税 | 森林環境税 | |
|
均等割 |
所得割 |
||
|
町内に住所がある個人 |
○ |
○ |
○ |
|
町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 |
○ |
× |
× |
注:町内に住所や事業所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
課税されない人
均等割・所得割・森林環境税がかからない人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の人で前年の合計所得金額が135万円以下である人
均等割・森林環境税額がかからない人
・前年中の合計所得金額が次に掲げる額以下の人
扶養のない人 ⇒ 38万円
扶養のある人 ⇒ 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16万8千円+10万円
所得割がかからない人
・前年中の総所得金額が次に掲げる額以下の人
扶養のない人 ⇒ 45万円
扶養のある人 ⇒ 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円
税額の計算
納める税額は、均等割額、森林環境税額、所得割額の合計額です。
均等額
均等割額は、原則として町民税3,000円と県民税1,500円の合計4,500円に森林環境税額1,000円をあわせた5,500円です。
注:県民税均等割のうち500円は、「ひろしまの森づくり県民税」として森林保全のために平成19年度から令和8年度までご負担いただくものです。
所得割
個人の前年中の所得金額を基礎として、計算された税額をいいます。
所得割の税額は、次の方法で計算されます。
所得金額(注1) - 所得控除額(注2) = 課税総所得金額
課税総所得金額 × 税率 - 税額控除額(注3) = 所得割額
(注1)所得金額
所得割の税額を算出するうえで基礎となる所得です。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
所得税と同様に次の10種類があります。
○所得の種類と所得金額の計算方法
|
所得の種類 |
所得の内容 |
所得金額の計算方法 |
|
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
|
配当所得 |
株式や出資の配当など | 収入金額-負債の利子=配当所得の金額 |
|
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
|
事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
|
給与所得 |
給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得給与所得金額の計算 詳細はこちらをクリック |
|
退職所得 |
退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
|
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
|
譲渡所得 |
資産の譲渡により生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
|
一時所得 |
生命保険金、賞金、懸賞当選金、競馬などの払戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
|
雑所得 |
公的年金等や原稿料、講演料など他の所得にあてはまらない所得 |
次の1と2の合計額=雑所得の金額 1 公的年金等収入金額-公的年金等控除額公的年金等に係る雑所得の簡易計算表 詳細はこちらをクリック 2 1を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
(注2)所得控除額
納税義務者の個々の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかなど個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
なお、所得控除の内容は次のとおりです。⇒所得控除の内容へ(こちらをクリック)
所得割の税率
課税総所得金額に税率(町民税6%、県民税4%)を乗じた額が所得割額となり、この所得割額から税額控除額を差し引いたものが所得割税額になります。
所得割の税率
所得金額から所得控除額等を差し引いたものを課税総所得金額といいます。この課税総所得金額に所得割の税率を乗じて所得割額を算出します。
なお、税率は平成19年度から一律となっています。
課税総所得金額(A) × 町民税率(6%)(B) = 町民税所得割額
課税総所得金額(A) × 県民税率(4%)(C) = 県民税所得割額
注:課税総所得は、所得金額から所得控除額を差し引いたものです。
(所得金額) - (所得控除額) = 課税総所得金額(A)
【計算例(課税所得金額が180万円の場合)】
町民税の所得割額 = 180万円 × 6% = 108,000円
県民税の所得割額 = 180万円 × 4% = 72,000円
町民税所得割額(A×B) - 町民税分税額控除額(D) = 町民税所得割税額
県民税所得割額(A×C) - 県民税分税額控除額(E) = 県民税所得割税額
所得割の税額
所得割に係る税額は、上記「町・県民税の所得割額」から「税額控除(注3)」を差し引いたものが当該所得割の税額になります。
【計算例(課税所得金額が180万円の場合)】
町民税の所得割税額=(180万円×6%)- 3,100(D) = 104,900円
県民税の所得割税額=(180万円×4%)- 2,200(E) = 69,800円
(税額控除額)
1 配当所得10万円(a)の場合
(a)×1.6%(町:1,600円(D1))、(a)×1.2%(県:1,200円(E1))
2 調整控除(基礎控除のみ)
(所)基礎控除48万円-(住)基礎控除43万円=人的控除の差額5万円(a)
(a)×5% = 2,500円(町:1,500円(D2))、(県:1,000円(E2))
●町民税税額控除額 D1+D2=3,100円(D)
●県民税税額控除額 E1+E2=2,200円(E)
(注3)税額控除額
税源移譲による負担増の解消、配当所得や外国の源泉所得に対する二重課税を排除する趣旨等で定められています。
税額控除の種類については次のとおりです。
1 配当控除
株式の配当所得がある人で総合課税の適用を受ける人は、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。
注:私募証券投資信託等の収益の分配に係る配当所得については控除額が異なります。
- 課税総所得金額等の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
町民税:配当所得金額の1.6%
県民税:配当所得金額の1.2%
- 課税総所得金額等の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得
町民税:配当所得金額の0.8%
県民税:配当所得金額の0.6%
2 外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が差し引かれます。
3 調整控除
所得税と町・県民税では、扶養控除などの人的控除額が異なります。税源移譲によって控除額の差(下表参照)により個人の負担が増える場合がありますので、これを調整するため、町・県民税所得割額から次の額を減額します。
注:合計所得金額が2,500万円を超える人は適用されません。
- 町・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の人
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町:3%・県:2%)
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)町・県民税の合計課税所得金額
- 町・県民税の合計課税所得金額が200万円超の人
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町:3%・県:2%)
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)町・県民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
4 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年から令和7年までに入居された人で、所得税で住宅ローン控除(特定増改築によるものを除く。)を受けており、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で町・県民税所得割額から控除されます。
控除限度額は、原則として、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)ですが、特例的な措置として、平成26年4月~令和3年12月入居者(特定取得、特別特定取得、特例取得、特別特例取得、特例特別特例取得)については、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡充しています。
5 寄附金税額控除
地方公共団体に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人等のうち広島県の条例で定める寄附金のうち、2,000円を超える部分については、一定額を限度に所得割額から控除されます。また、地方公共団体に対する寄附金については、控除額の加算があります。
税額控除額は、上記1から5の町・県民税分のそれぞれの合計額が税額控除額のDおよびEとなります。
利子割
利子所得等に対しては、県民税利子割として、利子等の支払いの際、他の所得と区分して5%(他に所得税15%)の税率による一律分離課税を行います。
また、この場合の徴収(特別徴収)は、利子所得等の支払いをする金融機関が行います。
配当割
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、県民税配当割として、配当等の支払いの際、他の所得と区分して5%(他に所得税15%)の税率による分離課税が行われます。なお、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当等の所得は非課税とされています。(NISA)
また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の配当等の支払いをする者が行います。
なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくてもよいことになっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
株式等譲渡所得割
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して5%(他に所得税15%)の税率による分離課税が行われます。なお、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得は非課税とされています。(NISA)
また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の譲渡の対価等の支払いをする者が行います。
なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいことになっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
退職所得の特例
町・県民税の所得割は、前年中の所得について町が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当等の支払者が、退職者に退職手当等を支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する計算をし、支払額からその税金を天引きして、町に納入することになっています。
土地建物等の譲渡所得の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する町・県民税については、他の所得と分離して次のように課税します。
長期譲渡
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得を長期譲渡所得といいます。
なお、優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合は、別途課税の特例があります。
【一般の長期譲渡所得に係る計算方法】
譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(注:) =長期譲渡所得額(ア)
(注:)特別控除額 ⇒ 政策的に税額を軽減するために設けられた控除です。
(ア)×5%(町:3%・県:2%)
短期譲渡
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等に係る譲渡所得を短期譲渡所得といいます。
【一般の短期譲渡所得に係る計算方法】
譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(注:) =短期譲渡所得額(イ)
(注:)特別控除額 ⇒ 政策的に税額を軽減するために設けられた控除です。
(イ)×9%(町:5.4%・県:3.6%)
株式等の譲渡所得の特例
県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して、5%(町民税3%・県民税2%)の税率により課税が行われます。