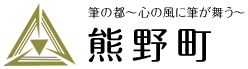ヤマウルシ

樹皮は、灰白色で縦に褐色の筋が入ります。あまり枝を分けず細かい枝がないことなど樹形も観察すれば、葉のない冬でもヤマウルシが分かります。
高さは3~8m。直径は普通5~10cmですが、町内の土岐城山で最大級の18.6cmを計測しています。
大きな奇数羽状複葉で、葉軸が赤みを帯びます。枝先に輪生状に互生し、傘状の姿になります。小葉はハゼノキなどに比べ丸みがあり、成木では普通鋸歯がありません。紅葉が見事です。
雌雄異株。5~6月、黄緑色の小さな花が密集した花序が葉腋から下がります。
果実は核果で偏球形、直径5~6mm。外果皮に黄褐色の剛毛が密生しているので、無毛のウ
ルシやハゼノキなどと区別できます。外果皮は剥れ易く、白いロウ質の中果皮が現われます。
熊野の地方名は「カブレノキ」。樹液に触れるとかぶれますが、近寄っただけでかぶれる人もあり、特に若葉の頃は注意が必要です。
北海道から九州に分布し、町内の山でよく見かけます。
ウルシの語源は「うるしる(潤液)」「ぬるしる(塗液)」で、転訛してウルシになったと言われます。
漆は中国・ヒマラヤ原産で、漆を採るため植栽され野生化したものもありますが、町内では見ていません。
【写真・文】
緑花文化士 冨沢由美子