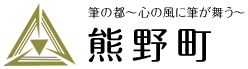フクラスズメ

前ばねは地味ですが、後ばねには美しい青色の帯があります。普通に止まっている時は後ばねは見えません。危険が迫った時、後ばねを見せて敵を驚かせ、その隙に逃げようとします。
成虫は年に2回、7~8月と10~11月に発生します。秋に発生した成虫は越冬するので、春にも見られます。普通種で、はねを開いた長さ(開張)は75~85mmほど。
幼虫は黄色に黒い縞模様があり気門の周りが赤い紋となって並んだどぎつい色彩で、白い長毛があります。
幼虫の多くは、体の色を周囲の色に似せ、目立たなくして敵から身を守ります。
目立つ幼虫は、毒を持っていたり、食べても味が悪いものが多く、食べた鳥などが二度と狙わないように、わざと目立たせて身を守っています。
幼虫は、カラムシ、コアカソ、ヤブマオなどイラクサ科の草を食べます。触ると上体を反らし、左右に激しく振って威嚇します。
ほぼ日本全土に見られ、朝鮮や中国、東南アジアなどにも広く分布しています。
脹雀蛾は、スズメガ科ではなくヤガ科の仲間です。
ヤガ科は大部分が夜行性なので、夜蛾(ヤガ)の名があります。「安芸熊野の自然誌」には町内で61種記録があります。フクラスズメ、オオトモエ、フタトガリコヤガなど数種類を追加します。
【写真・文】
緑花文化士 冨沢由美子