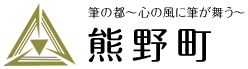イヌツゲ

子どもの頃、庭に植えられていた木の名前を尋ねると、父は「ネズミモチ」だと教えてくれました。熊野のほか、呉市、庄原市などでも、この名で呼ばれます。
名は、樹皮を叩き粘りを出してネズミを捕らえたことから付いたと言われます。鳥黐としても使いました。
「ヨメノサラ」と呼ぶ地方もあります。長さ1.5~3cmの小さな葉を、お嫁さんが使う皿に見立てた名です。
常緑で高さ2~3m、最大7m直径15cmになります。町内で直径10cm以上の大きな木が群生しているのは、竜王山の山頂あたりです。
よく枝を分けて小さな葉を密につけ強い刈り込みにも耐えるので、庭木、生け垣、盆栽、また鳥や動物などの姿に刈り込んで作るトピアリーにも使います。
葉は互生します。光沢があり滑らかで、低く目立たない鋸歯があります。
6月頃、葉の腋に直径4mmほどの白い花が咲きます。雌雄異株で、雄花は数個ずつ雌花は1個ずつ付きます。
果実は直径5~6mmの球形で10~11月に黒熟します。
本州、四国、九州に分布。町内で普通に見られます。
多くの園芸品種があり、マメツゲは葉が強く反り返り丸く膨らんで見えます。
和名「犬黄楊」は、ツゲに似るが材質が劣るので付いた名です。ツゲはツゲ科で、葉は対生しています。
【写真・文】
緑花文化士 冨沢由美子