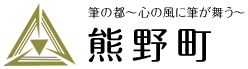ハタザオ

根元から出た葉が地面に張り付くように円く広がったものをロゼットと呼びます。バラ、ローズと同じ語源で、バラの花のような形を意味しています。ロゼットの多くは、キク科やアブラナ科などの草の冬超しの姿として見られます。冬の乾燥した寒風を避け地熱を利用し、日光をしっかり受けて養分を蓄えます。
葉の形や色、厚み、毛などの特徴を観察すると、ロゼットでも種類が分かります。ハタザオの根出葉は、羽状に中裂しています。先の方が幅が広くて尖らず、両面に星状毛などの毛が密生していて、白っぽい緑色です。
春になると、一本だけ真っ直ぐに茎を伸ばします。高さは50~100cm。
茎につく葉は、根出葉とは違って無毛で裂けず、茎を抱くようにつき、上方ほど小さくなります。中部より上は全体無毛です。
4~6月、茎の先に黄色を帯びた白色の小さな十字状花が総状に咲きます。
実は細く、長さ4~6cmもありますが、上向きに茎にぴったりと沿っています。
このような草の姿から、「旗竿」の名が付きました。
発芽し、ロゼットで冬を越し、春に開花し実をつけて枯れる二年草です。
日本全土の日当たりの良い草原、河原などに分布します。町内では、新宮の熊野川の土手で見られます。
【写真・文】
緑花文化士 冨沢由美子