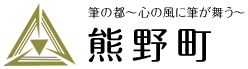コウヤボウキ

今年伸びた枝先に、白いリボンを束ねたような優美な頭花を1個つけます。小さな花が13個ほど集まっていて、1個の花は細長い筒状で5つに深く裂け、裂片が反り返っています。9月下旬から11月上旬に咲き、頭花の直径は約2cmです。
タンポポのような冠毛をつけた冬の姿も魅力的です。冠毛は褐色ですが、時に美しいピンク色があります。
落葉低木で高さ60~90cm。今年伸びた枝には丸みのある葉が互生し、2年目の枝には節毎にやや長い葉が3~5枚集まってつきます。枝は2年で枯れます。
関東地方より西に分布し、山のやや乾いた所に生えます。熊野町で広く見られます。
高野箒の名は、高野山で竹箒の代用とした事から付いたと言われます。真言宗総本山の高野山では、弘法大師の願により、柿や桃、竹などは利益につながるとして植栽を禁じられた、また弘法大師が大蛇を竹箒に封じ込めたため、竹箒の使用が禁じられたとも伝えられています。
古名は玉箒で万葉集などに出ています。新春、皇后が蚕の床を掃き蚕神を祭り、五穀豊穣を祈ったそうです。
2年目の枝の節毎に頭花をつけるナガバノコウヤボウキは町内にはありません。
キク科は最も進化した仲間で、木は少なく、日本には数種あるだけです。
【写真・文】
緑花文化士 冨沢由美子